ネットで風評被害を受けたらまずは何をするべきか?

現代社会では、企業でも個人でも日常的にネットを利用していることが普通ですが、ネット上では悪意あるコメント投稿が行われることが非常に多いです。この場合、放っておくと誹謗中傷の内容が広がって、被害が大きくなってしまうので、対処をする必要があります。
ただ、実際にはどのような対処をすれば良いのかがわからないことが多いでしょう。
そこで今回は、ネット上で悪意あるコメントを投稿されたら、まず何をすべきかについて、解説します。
証拠を残す
ネット上で自社や自分のことについて悪意あるコメントの投稿が行われていたら、ショックを受けて呆然としてしまうことがあります。
まずは、なぜそのような投稿が行われたのか、誰が書き込みをしたのか、心当たりを考えましょう。明らかに誰が書いたのかがわかる場合には、その人に連絡をとって、問い詰めたり削除させたりすることができます。
ただ、多くのケースでは、投稿者を特定することは難しいです。ネット上では匿名で投稿ができるため、たくさんの人が匿名で書きたい放題の投稿をしていますし、利用者もとても多いからです。
会社に対する嫌がらせの投稿が行われた場合でも「ライバル社がやったのだろう」と思っても、実際に投稿者を特定するところまではできないことが普通です。
そこで、法的な対処をすることを考えなければなりません。そのためには、まずは証拠をとることが重要です。
今後削除依頼を出したり、投稿者の情報を特定して損害賠償請求を行ったりするためにも、必要なのは証拠です。今は記事が残っていても、賠償請求を行う前にいきなり削除されては証拠がなくなってしまいます。そこで、悪意あるコメントが書き込まれている画面を写真撮影したりプリントアウトしたりして、証拠保存しましょう。そして、URLも控えておきましょう。
サイト管理者に削除依頼を出す
証拠をとったら、次に記事を削除させることが必要です。悪意あるコメントの投稿が残っていたら、その情報が世間に広がって自社や自分の評判が低下してしまうからです。
そのためには、まずはサイト管理者に削除依頼を出しましょう。掲示板やツイッターなど、各サイトには、サイト管理者に削除依頼をするための専用フォームがもうけられていて、それに記入して管理者に連絡ができるものが多いです。
そのような専用フォームがある場合には、利用してサイト管理者に削除依頼の連絡ができます。フォームがない場合には、掲示板の運営者にメールなどで直接連絡を入れます。このとき、どの部分が問題になっているのか、どのような権利侵害があるのかについて、第三者にもはっきりわかるように説明することが重要です。
自分では名誉毀損だと感じていても、事情を知らない人にまでわかりやすく説明するのは意外と難しいものです。
事実と異なることが書かれているなら、実際のところはどうなのか、それに対して書かれている内容はどうなのか、そしてそれによって自社がどのような損害を受けるのかなどについて、詳細にわかりやすく書き込みましょう。
弁護士に仮処分を依頼する
サイト管理者に削除依頼を出しても対応してもらえない場合や、当初からサイト管理者の対応に期待していない場合には、弁護士に仮処分を依頼して記事削除をしてもらう方法があります。
その場合には、ネット問題に強い弁護士を探して、裁判所に対し、記事削除を求める仮処分を申請してもらう必要があります。
裁判所で権利侵害と記事削除の必要性が認められたら、削除命令が出るので、サイト管理者が任意での削除に応じてくれなくても投稿を消してもらうことができます。
このように、ネット上で悪意あるコメントの投稿を受けた場合には、放っておくのではなく対処をとる必要が高いです。まずは証拠をそろえてから、すぐにネット問題に強い弁護士に相談に行くことをおすすめします。

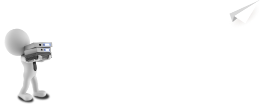


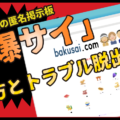







 LINEで
LINEで